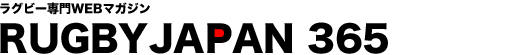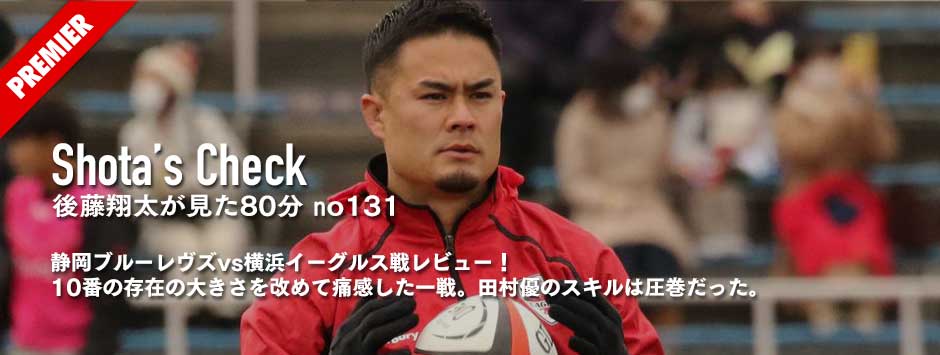19日は静岡・磐田で静岡ブルーレヴズ(以下、ブルーレヴズ)と横浜イーグルス(以下、イーグルス)の試合をJスポーツで解説させていただきました。僕にとっては2月5日のブレイブルーパス東京vs静岡ブルーレヴズに続く解説でした。
前節の敗戦から接点の攻防にこだわった両チームの戦い

静岡ブルーレヴズ・堀川隆延監督
ブルーレヴズはその試合に26ー59で敗れました。一方のイーグルスは前節21ー50でスピアーズ船橋に敗れていました。どちらもパワフルなFWを前面に出してくる相手にフィジカル勝負でやられたという同じような負け方をして、BYE週による2週間のインターバル=修正期間を経てこの試合に臨んだわけです。
試合前には、キヤノンのアシスタントコーチをしている佐々木隆道と立ち話をする機会があったのですが、隆道は「やっぱりラグビーは本質的なとこで負けちゃダメっすね。タックルはこの2週間、改善できるように徹底してやってきました」と言っていました。ブルーレヴズからも同様のことを聞きました。両チームとも、接点の攻防にはこだわってこの試合に臨んだはずです。
僕がラグビーの試合を見るときに目安にしているのは、ゲームを構成するいくつかの重要なパーツ、たとえばスクラム、ラインアウト、モール、アタック&ディフェンスのフェイズプレー、カウンターアタック……といった要素ごとに、どちらのチームが優位性を持っているか、その優位性を活かすゲーム運びが出来ているか、それによってどう勝負が決して行くかということです。ですが、この試合では、各要素における優劣の関係が頻繁に入れ替わりました。