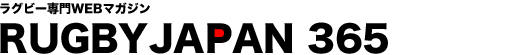スポーツライター・永田洋光氏が独自の視点でRJ365だけに書きおろした最新コラムを公開する新コーナー「nagata's eye」。記念すべき第1回は、サッカーワールドカップブラジル大会の一場面から筆者の深い考察が垣間見れる注目作。
ナショナル・アンセムは「みんなが歌う」一体感が求められる

RWC1995開幕時の様子
ラグビーファンにはお馴染みのテストマッチ前の国歌(アンセム)演奏。
誇りをかけた一戦に臨む両チームの闘志が凝縮される瞬間だ。
1995年にラグビーW杯開催を控えた南アフリカ代表スプリングボクスは、前年秋のヨーロッパ遠征では、国歌に対して非常に複雑な反応を見せていた。
発足したばかりのネルソン・マンデラ政権が定めた新しいアンセムは、反アパルトヘイト運動のプロテストソングだった『ネコシ・シケレリ・イ・アフリカ(神よ、アフリカに祝福を)』と、白人政権時代に国歌とされていた『ディー・ステム(叫び)』を1つにつなげたもの。WTBチェスター・ウィリアムズを除けば全員が白人だったスプリングボクスにとって、国歌の最初の部分=『ネコシ・シケレリ・イ・アフリカ』は、「テロリストの歌」(映画『インビクタス』のなかで白人選手が言ったセリフ)であり、忠誠心を尽くすのが非常に困難だったのだろう。NHKのBS放送で流れた映像では、多くの選手が顔を背けたり、なかにはつばを吐く選手までいたと記憶している。見ていて、あまり気持ちのいいものではなかった。

RWC1995開幕時の様子
それが1995年W杯開幕戦では、全員が直立不動の姿勢を保ち、口蓋の構造的に白人には発音が難しいとされるズールー語などアフリカに古来から伝わる言語の歌詞を歌おうと努力したりしていた。キャプテンのフランソワ・ピナールが働きかけたことによって実現した、この忠誠心の発露は、『ディー・ステム』に対して憎悪を抱く黒人層(彼らをテロリストとして弾圧してきた政権の歌だから当然だ)をも動かし、スプリングボクスが優勝したこともあって、W杯は新政権で船出したばかりの『レインボー・カントリー』を1つにするのに多大な貢献をした。
あるいは、1999年W杯の準決勝では、フランスが選手同士お互いに腕を回して体を密着させ、ギュッと固まって『ラ・マルセイエーズ』を歌ったのに対して、優勝候補のニュージーランドは、なんとなく選手間の距離が遠く、ただ漫然と並んでいるだけのような印象だった。横一列に並んだ両チームの、それぞれの列の長さがまったく違って見えた。トゥイッケナムのバックスタンドに設けられた記者席から見ていた私には、長さの比がフランス1対ニュージーランド2ぐらいに見えたのである。
「大丈夫なのか、オールブラックスは?」と思っていたら、案の定、試合はフランスが潜在能力を全面的に開花させて43−31と快勝。フランスに蹂躙されるオールブラックスの映像を見たニュージーランドの子どもたちの心に傷が残った、という報道も後に出たほど、その番狂わせは衝撃的だった。先日幕を閉じたばかりのサッカーW杯ブラジル大会で言えば、やはり準決勝でドイツが開催国ブラジルに7−1と大勝したのと同じようなショックを全世界に与えたのである。
ウェールズ代表がテストマッチを前に、彼らのアンセム『ランド・オブ・マイ・ファーザーズ』を熱唱するように、スコットランド代表も『フラワー・オブ・スコットランド』を熱唱するし、1999年に痛い教訓を得たニュージーランドも、マオリ語→英語の順で『ゴッド・ディフェンド・ニュージーランド』を一生懸命歌う。日本代表も、外国出身の選手たちも『君が代』の歌詞を覚えて、日本人選手といっしょになって歌う。
それほど試合前のアンセム演奏時には「みんなで歌う」一体感が求められるのだ。
同じ光景はサッカーW杯でも顕著だった。
ブラジルは、これ以上ないほどエモーショナルに選手も観客も一体となって、90秒以上は演奏をしないと取り決めがあるにもかかわらず、音楽がやんでもアカペラで国歌を歌い続けた。準優勝したアルゼンチンも、まったく同じような感じだった。
やっぱり、これがフットボールのアンセム演奏なのだな……と感心していたら、真逆の例外があった。
前述したドイツ代表である。