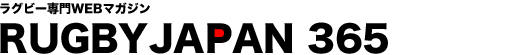昨年春にNTTコムを退社、オーストラリア・シドニーの名門クラブ、ランドウィックで武者修行していたSO君島良夫が、今度はアメリカ西海岸の名門クラブ、OMBACでプレーすることになった。

君島は、清真学園から同志社大を経て2007年に当時トップイーストのNTT東日本に入社。中学時代にブラジル留学も敢行したほどの本格的サッカー少年だった時代に身につけた正確なゴールキックで2010年のトップリーグ昇格の原動力となり、昇格1年目の2010年にはリーグ7位の127得点、3年目の2012年には同3位の140得点。

2011年6月には、東日本大震災復興チャリティマッチでトップリーグ選抜のSOとして日本代表(JapanXV)と対戦した。2013年度もリーグ戦14試合中13試合に出場し、99得点はリーグ7位。トップリーグを代表するSOの1人だったが、シーズン終了後の昨年3月、チームから戦力外通告を受け、新天地を求めてNTTを退社。
トップリーグの他チームに移籍するには時期が遅く、条件が悪かったことから国外でのプレーを決意し、伝手をたどってチームを探すと、NTTコムの元チームメートで、エージェントをしているティム・レネヴェの紹介で、オーストラリア・シドニーの名門クラブ・ランドウィックでプレーできるチャンスを得た。君島は6月に渡豪した。

「デビュー戦はランドウィックの3軍でしたが、相手にジョージ・スミスの弟がいた。僕はジョージとは仲が良くて、一度東京で会ったことがあったんです。試合中にアイコンタクトしたりしましたよ。『久しぶりだな』って感じで(笑)。トップリーグでプレーしていた経験のある選手もけっこういました」
デビュー戦の会場は、1987年の第1回ワールドカップ準決勝、伝説の名勝負と言われるフランスvsオーストラリアの舞台となったコンコルド・オーバルのあった場所にあるシドニースタジアムだった。セルジュ・ブランコの伝説のトライの現場だ……
「それ、いろんな人に言われましたけど、僕は全然知らないんです(笑)」
デビュー戦を3軍で戦った翌週には2軍に引き上げられた。
「クラブレベルのラグビーは、日本ほどのスピード感はない。それよりも、もっとパワフルな感じでしたね」
オーストラリアでは日本と異なり、2軍も3軍もそのグレードの大会があり、1軍と同様にリーグ戦を行い、プレーオフ、ファイナルと試合は進む。オーストラリアの国内シーズンはすでに開幕して3ヶ月が経過していて、チームの骨格はできあがっていた。さらにシーズン終盤に向け、ワラタスのメンバーがクラブに戻ってきた。結果として、8月のシーズン終了まで、ランドウィック1軍でプレーする機会はなかった。

17歳でスーパーラグビーに、18歳でテストデビューを飾った世界ラグビーのワンダーボーイ、ジェームズ・オコーナーをはじめ、若き天才が次々と現れるオーストラリアの選手育成の秘密を垣間見る思いだ。
ランドウィックのシーズンは8月に終了した。オーストラリアのラグビーシーズンはオフに入った。しかし君島は日本に帰国せず、そのままシドニーに残った。
「英語の勉強を続けたかったし、せっかくオーストラリアまで行って、人とのつながりを作れたので、それをもっと大きくしていきたいと思った。それと、将来のことも考えて、コーチの勉強もしたかった」

そこには君島ならではの着眼点もあった。日本ではキッキングコーチのスペシャリストがほとんどいない。海外で、専門的なコーチングスキルを学んで持ち帰った人もほとんどいない。
「ラグビーユニオンだけじゃなく、オーストラリアでは一番盛んなAFL(オーストラリアン・ルールズ・フットボール)のキッキングコーチに教わりにも行きます。キックキャッチの練習も盛んなので、そこも勉強したいです」
これまで、幾多のコーチ志望者が日本からオーストラリアに渡り、研修を受けてライセンスを取得した。しかし、選手として腰を据えてプレーし、オフシーズンも現地で長く過ごして文化にどっぷりと触れ、さらに異種フットボールまでスキル研究の触手を伸ばした人物はいなかっただろう。

かくして、8月にオーストラリア国内シーズン終了後も、君島はオーストラリアでラグビー&フットボールを学び続けた。
「4ヶ月近いオフを過ごしました。日本では味わえない、久々に長いオフを経験しましたね。でも、9月からは、『オージータグ』といって、ラグビーリーグ(13人制)ルールのタグラグビーの大会があって、そのチームに入って毎週していました。だから完全なオフではなかったかな」
なお、アメリカのクラブのシーズンは1月24日にスタートするが、各種手続きの関係で、2月上旬の渡航となるそうだ。アメリカでプレーした後は、日本のトップリーグでのプレーも視野に入れつつ、オーストラリアに戻る選択肢も考えているようだ。ラグビー選手、未来のラグビーコーチとしてだけでなく、異文化の中で素晴らしく充実した時間を過ごしている、31歳のちょっとアダルトな青年が、実に頼もしい。若者の国内指向が指摘される現在の日本から見ると、そのチャレンジ精神がまぶしく見える。何より、気負いなくそれを楽しむフットワークの軽さが、何ともカッコイイ!
「ホントに思いますよ。いい時期に戦力外にしてもらえました」
君島良夫、31歳。青春のサーキットを、まだまだ周回し続ける。
 大友信彦 大友信彦1962年宮城県気仙沼市生まれ。気仙沼高校から早稲田大学第二文学部卒業。1985年からフリーランスのスポーツライターとして『Sports Graphic Number』(文藝春秋)で活動。’87年からは東京中日スポーツのラグビー記事も担当し、ラグビーマガジンなどにも執筆。プロフィールページへ |