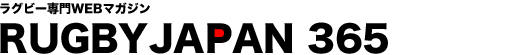ジョージア代表戦に勝利し秋のテストマッチシリーズを1勝4敗で終えたラグビー日本代表(2年目のテストマッチの通算成績は5勝6敗)。11月24日、羽田空港で、ジョージアから帰国したばかりの永友洋司チームディレクターとエディー・ジョーンズHCが「リポビタンDツアー」の総括会見を行った。
永友洋司TD「強豪国との差を体感でき、何を改善すべきかが明確になったことが財産」
ご存じの通り、(遠征の)成績はジョージア代表戦での1勝のみとなりました。ティア1の上位国と対戦する中で、世界ランク1~4位の強豪国との距離は依然として大きいと感じた。その差を実際に体感でき、チーム全体、何を改善すべきかが明確にできたことが、今後に向けて大きな財産になった。加えてJAPAN XV、学生のJTSという下のカテゴリーと、試合に出られなかった選手を集めた中から初キャップ得た選手が出て、世代交代、選手層の厚みといった上でも重要な遠征だった。
下のカテゴリー、JAPAN XVから上がってきたCTBチャーリー・ローレンスは外から見ていても攻守にわたって素晴らしい成長を遂げた。また今回の遠征ではPR竹内(柊平)、為房慶次朗、LOワーナー(・ディアンズ)、SO李(承信)、CTB(ディラン・)ライリー、WTB石田(吉平)といった選手が継続的に試合に出続けた。80分、フルに出場し、中心となってチームを牽引してくれたことは大きな財産になった。一方で離脱した選手が多かったが、ただ筋肉系のケガでの離脱が少なかったのはメディカル中心にスタッフのサポートがあったからだと思います。(世界の強豪とは)ストレングスに関しては大きな差があると考えています。今後、リーグワン、大学と連携して、スケジュールの調整、選手のウェルフェアをクリアにしながら、足りなかったものを補っていきたいと思っております。
エディー・ジョーンズHC
昨年、同じ時期に私たちはここに座っていましたが、当時の現状と目指す姿との間には大きな隔たりがありました。今も隔たりは残っていますが、この12ヶ月間でその差を縮められたと感じています。
その理由として、チームの(選手)層が厚くなったことが挙げられます。例えばルースヘッドプロップのポジションを見ても、主力選手3~4名を失いました。それでも左PR小林賢太のような選手が、(ジョージア代表のような)世界最強クラスのスクラムを相手に80分間フル出場を果たしました。
HOでは、佐藤健次が大学を卒業したばかりですが、江良(颯)と原田(衛)を失ったツアーで非常に立派な働きを見せました。このような例は他にもあります。